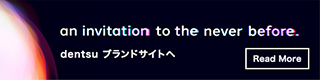「第87回日本循環器学会学術集会」が、福岡国際会議場をメイン会場として、2023年3月10日から3日間にわたり開催された。日本循環器学会(Japanese Circulation Society:JCS)は、1935年に設立された、会員数3万人を超える日本有数の医学系学会である。JCSは、心臓や血管関連に対応する循環器科領域において社会的な役割を担うが、日本脳卒中学会や関連学会と共同し、健康寿命の延伸を目的とした「脳卒中と循環器病克服5ヵ年計画」の作成や、「脳卒中・循環器病対策基本法」の成立といった、幅広い活動も行っている。
昨今のコロナ禍のため、毎年3月に実施される学術集会は、2020年、2021年、2022年の3回にわたり完全オンラインまたはオンライン中心の開催となり、参加者同士のリアルな交流は大きく制限されていた。しかし2023年の今年、後日のオンデマンド配信はあるものの、リアルタイムでの体験を中心に据え現地開催された。開催期間は好天に恵まれ、参加者がマスクを着用しているという例年との違いはあるものの、久しぶりに対面での交流を楽しむ参加者の姿も見られ、コロナ禍前に近い盛り上がりを見せていた。
2023年の学術集会におけるテーマは、「New Challenge with Next Generation」が掲げられた。「Next Generation」とは、これからの循環器病学を担う次世代の医師、研究者、メディカルスタッフを含めた多様な人材、そして循環器病診療および研究を支える次世代のテクノロジーを指す。そのテーマを体現するように、会期中は若手医師やメディカルスタッフたちによる幅広い内容のセッションをいくつも見ることができ、立ち見が出るほどの大盛況であった。ここではそのセッションのいくつかを紹介する。
会長特別企画 U-40部会企画
「JCS EARLY CAREER CHAMPIONSHIP」
JCSダイバーシティ推進委員会は、女性医師や若手医師を積極的に委員会メンバーに加え、さまざまな活動を展開している。本委員会の下部組織となるU-40部会では、若手医師に循環器の魅力を周知させるため、全国の各支部に若手委員会を設置し、若手医師の活性化に向けた支援を行っている。その一環として、今回の学術集会では「JCS EARLY CAREER CHAMPIONSHIP」が初めて実施された。これは、北海道地方会や東北地方会など日本全国を9つに分けた各地方会で、若手医師たちがそれぞれ発表を行い、地方会ごとで最優秀賞を決めたのち、受賞者の若手医師たちが学術集会に集結し、その中からさらに全国一位を競うというセッションで、審査は、各地方会の代表となる先輩医師が担当した。また、会場との一体化を目的として、聴講者がスマホで2次元コードを読み取り、投票に参加できるという取り組みもなされ、参加者の気持ちを盛り上げた。授賞式は翌日、大きな会場で厳かな雰囲気で行われたが、来年以降も実施予定とのことで、若手医師にとっては励みになる企画であった。
しくじり体験から学ぶ『女性の働きやすさ』とは
――新時代への心からのメッセージ
本プログラムも、上述のダイバーシティ委員会により企画されたもので、若手の女性循環器医会員の数が増加する昨今、非常に興味深いセッションであった。アンケート調査の結果や、実際の労働環境、また女性医師に指導した男性先輩医師からの講演などもあり、幅広い情報を共有しあう講演となった。
OncoCardiology:
診断と治療 Up-to-Date
2017年に日本腫瘍循環器学会が設立された。これは近年、心血管系疾患を合併するがん患者が年々増える中、特に進行がんの治療に際して、循環器医とがん治療医の診療上の連携がより必須となってきた背景がある。さらに2023年は「Onco-cardiologyガイドライン」が発刊された年ということもあり、今回はそれを踏まえたシンポジウムとなった。腫瘍・血液内科の医師も登壇し、これからの腫瘍循環器学に向けて重要な内容となった。
今だからこそ考える:
循環器領域における健康の社会的決定要因について
このプログラムには、「健康の社会的決定要因(Social Determinants Of Health:SDOH)」の研究者である、近藤尚己氏(京都大学大学院医学研究科社会疫学分野/東京大学未来ビジョン研究センター)を登壇者に迎え、近年、医学生に学修目標として設定されたSDOHについてのパネルディスカッションが行われた。病気は、生まれ持った体質や遺伝子などの生物学的要因によって決まると考えられがちだが、その要因による割合が群を抜いて高いわけではなく、生活習慣や、医療制度や社会状況なども同程度の割合と考えられている。つまり、生活習慣の形成は、家庭環境や成育歴によっても左右されるため、社会的要因が一人ひとりの健康に与える影響は非常に大きいと言える。こうしたSDOHに関する深い造詣を持つ近藤氏の解説が聞けるとあり、本プログラムでは、300名が入る会場でも立ち見の場所がないほど、幅広い職種の聴講者が詰めかけていた。