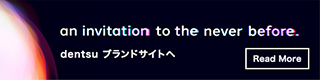「空気圧制御」で、“神の手”レベルの手術を目指して。
次世代ロボットが切り開く医療の未来とは?
医師不足が深刻化の一途をたどる、日本。同時に都市と地方、大病院と中小病院の間の医療格差、診療科の偏りなども大きな課題です。
これらのソリューションの1つとして注目を浴びているのが、医療分野におけるロボットの活用。医師が3D画像を見ながら遠隔操作によってロボットを動かし、手術を行う「手術支援ロボット」は、世界的にも飛躍的な進化を遂げ、多くの現場で活用されています。
今回は、この「手術支援ロボット」の分野で、業界に新しい風を吹かせているリバーフィールド株式会社の代表取締役社長 只野耕太郎氏のもとを、メディカル・ヘルスケア領域の専門的な内容を分かりやすく伝えることに強みを持つ、株式会社電通メディカルコミュニケーションズの代表取締役社長 林剛が訪問。より円滑で精緻な手術を可能にする「空気圧」を用いたロボットの開発を成功させた只野氏のこれまでの道のりや、医療領域におけるテクノロジー活用の可能性などについて、じっくりとお話を伺いました。
1/1000秒単位で空気圧を操る、独自技術を搭載した手術支援ロボット
林:電通メディカルコミュニケーションズはメディカル・ヘルスケア領域に特化し、患者さんやそのご家族をはじめとする、全ての人たちのより良い生活の助けとなれるように、さまざまなソリューションを提供してまいりました。ですから、手術支援ロボットの開発を通じて、患者さんや医療従事者を支えようとする御社の取り組みにも非常に共感しており、お話を伺うことを楽しみにしていました。よろしくお願いします。早速ですが、リバーフィールド株式会社で開発している手術支援ロボットは、空気圧を用いた技術を実装していると伺いました。
只野:はい。私どもの会社は2014年に東京工業大学と東京医科歯科大学発のベンチャーとして設立し、手術支援ロボットを開発してきました。2015年には、空気圧を用いた世界初となる内視鏡ホルダーロボット「EMARO」を国内でリリース。従来の内視鏡を使った手術では、助手の医師が内視鏡を持ち、執刀医の指示に従って動かす必要があるのですが、このロボットはその助手の代わりを務めてくれるんです。手術者はヘッドセットを装着し、その頭の動きに連動して内視鏡が動くので、直感的な操作によって安定した視野を得ることができます。
「EMARO」をリリースした後も、低侵襲外科手術(内視鏡などを用いた、体への負担が少ない手術)を支援するロボットの開発を進めています。2023年には、最新の低侵襲外科手術用支援ロボットを発売予定です。いずれも、空気圧を精密制御する当社独自の技術が実装されています。

林:御社のロボットにしか実装されていない、世界初の技術なんですね。空気圧制御の技術を用いた御社の手術支援ロボットは、他のロボットとどう違うのでしょうか?
只野:一般的な手術支援ロボットは「電気モーター式」である一方、当社のロボットは「空気圧制御式」を採用しています。空気圧制御式は、「力覚(りきかく)」を操作する医師に正確に伝えることができるので、より滑らかに柔らかく、安全に手術を行うことができます。

林:先ほど実際に、ロボット操作の体験をさせていただきました。鉗子(かんし)でつかんでいるにもかかわらず、本当に自分の手で物をつかんでいるような感覚がして驚きました。

只野:物を触ったときにザラザラしているとか、冷たいと感じる感覚は「触覚」と呼ばれますが、このロボットがフォーカスしているのは「力覚」です。物と接触したときの力のかかり具合や重さという力覚を研ぎ澄ませることによって、よりリアルな接触感覚が実現できるんです。
既存の手術支援ロボットですと、モニターで術野(手術を行っている時、目で見える範囲)を見ることはできるものの、力覚がないため視覚だけに頼った手術をせざるを得ません。そのため、見えている範囲外での異常を知ることができず、知らないうちに鉗子が周囲の臓器に当たり、大出血を起こして患者さんが亡くなってしまうという可能性もあります。
林:「力覚」があるかどうかが、最大の強みなんですね。技術の仕組みについて、もう少し詳しく伺えますか?

只野:空気圧を精密制御する技術は、自転車の空気入れをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。筒の中にピストンがあって、そこに空気を入れるとピストンが押され、その力によってロボットが動く仕組みです。このときにかかる圧力の変化をセンサーが感知して、操作している医師の手に伝達されます。手の役割をするロボットの鉗子が臓器などをつかんでいるのですが、どのくらいの力でつかんでいるのかが繊細に伝わるため、より手技に近い感覚で手術が行えるという利点があります。
つまり、圧力の情報と鉗子がどの位置にあるのかという情報をセンサーで読んで、それらの関係を整理し、空気を送る量を精密に調整しながら、ロボットの動きを制御するという仕組みです。現在は、1/1000秒単位で空気圧の状態を読み取り、細かく動きの修正を繰り返して操作しています。
これまで、空気圧を用いたロボット技術は、「物を押して移動させる」といった単純作業の現場ではよく使われていたのですが、医療の分野で活用するのは難しいとされてきました。なぜなら医療の分野では、桁違いに精密で複雑な制御が不可欠だからです。空気圧制御の仕組みを手術支援ロボットに応用するなんて不可能だと思う人も多いでしょう。しかし当社はさまざまな知見と開発努力を積み重ねることで、それを可能にしています。
より良い医療の提供と外科医不足の解決、患者と医師どちらにもメリットを生む

林:ところで、御社がこの技術にフォーカスして専門的に開発を進めてきたのには、どのようなきっかけがあったのでしょうか。只野社長は大学の研究者でいらしたわけで、そこから起業に至った経緯も含めて教えてください。
只野:当社の創業メンバーは4名で、そのうちの1人、現在はエグゼクティブアドバイザーを務める川嶋健嗣は、私の大学での指導教員でした。当時は東京医科歯科大学と東京工業大学の二校で医療と工学の連携を進めようという雰囲気が高まっていて、それまで行っていた空気や流体の研究から、手術支援ロボットへと研究テーマを広げていったのです。
私はその研究を修士課程から始めて、博士の学位も取得し、研究の面白さにハマって教員にまでなりました。当初は、研究で培った成果をどこかの企業に引き取ってもらい、製品化して世の中に生かせないかと考えていました。それでさまざまな企業と話をしたのですが、医療分野であることのリスク、利益を得られるのかという懸念もあったようで、結局話はまとまらなかったんです。そうした折、どうしようかと悩んでいた時に飛び込んできたのが、文部科学省の「START」という大学発ベンチャーの起業を支援するプロジェクトの話。そこで採択を受けたことが起業のきっかけです。
林:川嶋先生の研究室がもともと空気や流体の研究をされていたとのことですが、その研究をベースにして、空気圧を用いた手術支援ロボットに転用しようとお考えになったのですか?
只野:はい、空気圧をロボットに応用する研究は既に始まっていて、当時は手術用ではなく建設機械を遠隔操作するロボットでした。手術支援ロボットへの転用は、そうした中で、新しいテーマを求めていたことが1つの理由です。それに加えて、川嶋先生が手術支援ロボット「ダビンチ」のスペシャリストの先生と話をする機会を得たことも大きなきっかけでした。アメリカのIntuitive Surgical社が開発した「ダビンチ」は、世界的に大きなシェアを誇っている、この分野のパイオニア的な存在です。その対話の中で、手術や外科領域のロボット開発に興味を持ったんです。
私自身、空気圧の研究をする中で、「空気圧は力を検出したり、制御したりするのに向いているんじゃないか」という考えを深めていきました。そうした点と点が1つの線につながって、空気圧を手術支援ロボットに使ってみることにしたのです。

林:なるほど。さまざまな状況が絡み合って、空気圧を用いた手術支援ロボットの開発がスタートし、起業へとつながっていったわけですね。聞いていてワクワクします。ところで現在の日本においては、医療分野へのロボットの導入は当たり前になっているのでしょうか?
只野:かつては「ロボットなんて」とおっしゃる医師も多かったのですが、現在ではかなり認知されてきて、「当院にも欲しい」という声がたくさん聞こえてきます。日本は外科医不足で外科医や医療スタッフの負担が過剰になっている現状がありますので、その負担を減らすという意味で、ロボットは大いに貢献できると考えています。
また、最近は患者側からも「ロボットで手術をしてほしい」というリクエストが増えてきました。それだけロボット手術に対する信頼感が強まっているということではないでしょうか。実際、医師の手が届かない術部をマジックハンドのように機械を用いて手術する「腹腔鏡手術」の分野は、ロボットを使うことで簡単に、確実にできることが証明されています。
林:ロボットの進化によって手術が簡単にできるようになれば、患者さんの負担もさらに軽減されますね。手術支援ロボットが広く受け入れられるようになった直接的な背景には、何があるのでしょうか?
只野:ロボット手術の保険適用が可能になったことは大きいですね。手術支援ロボットによる手術の件数が増えてきて、きっちりエビデンスが積まれていった結果、保険適用の範囲が広がり、導入したいという病院が増えてきたのだと思います。
林:日本と比べて、海外の手術支援ロボットの普及状況はどうなのでしょうか?
只野:アメリカは、手術支援ロボットの代表格である「ダビンチ」が生まれた国でもあり、承認制度の承認に必要な期間も日本より比較的短い傾向があるので、多くの場面でロボットが用いられています。ヨーロッパでも医療用ロボットを開発するメーカーがたくさん出てきていて、世界中で手術支援ロボットのニーズは高まってきていると言えるでしょう。
林:その中でも、空気圧を用いて「力覚」を得て手術ができる技術というのは、御社だけのものなのですね。あらためてすごさを実感しています。
<まとめ>
世界的に医療の分野でのロボットの活用が増加し、技術革新も著しい中、リバーフィールドの手術支援ロボットがどれほど革新的なものなのか、只野氏のお話から伝わってきました。これから先、ロボットを使った手術が当たり前のものになれば、医療現場にとっても患者にとってもメリットが増え、より良い医療社会の創造にもつながっていくのではないでしょうか。
後編では、手術支援ロボットの導入や普及に立ちはだかる壁について、そして只野社長が目指す世界観などについて詳しく聞いていきます。
※2022年9月15日 Transformation SHOWCASE にて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。