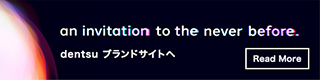2022年10月14、15、16日の3日間にわたり第84回日本血液学会学術集会が福岡国際会議場(福岡県福岡市)にて現地及びオンラインのハイブリッド形式にて開催された。日本血液学会は80年を超える歴史を持ち、基礎医学及び臨床医学の双方からわが国の血液学の発展に貢献し続けている学会である。
今学術集会では、テーマやスローガンは設けずプログラム全体がメッセージとされた。これは、「メッセージを言葉にするとその意味が限定されてしまうため、参加者それぞれにメッセージを埋めてもらいたい」という開催者の思いが反映されたものである。学術集会のプログラムは血液内科9領域と小児科で構成され、多くの研究成果の発表と活発な議論が行われた。
今回の日本血液学会学術集会では、ゲノム医療に関する演題も複数発表され、Special Symposiumとして造血器腫瘍によるがんゲノム医療について講演された。Special Symposiumは2部構成になっており、Part 1では坂田麻実子氏(筑波大学)及び前田高宏氏(九州大学)を座長に、米国研究者Jinghui Zhang氏(St Jude Children’s Research Hospital, USA)及びAsh A. Alizadeh氏(Stanford Cancer Institute, USA)より、米国において実践されている最先端のゲノム医療が紹介された。Part 2では、伊豆津宏二氏(国立がん研究センター中央病院)の進行のもと、造血器腫瘍分野におけるゲノム情報を基礎としたプレシジョン医療の具体的なイメージを参加者と共有することを目的として遺伝子パネル検査の概要の紹介と6症例の模擬エキスパートパネルが開催された。本レポートではわが国における造血器腫瘍分野におけるプレシジョン医療について、講演内容より一部抜粋して紹介する。
造血器腫瘍分野におけるプレシジョン医療
がん遺伝子パネル検査は、ヒトの体にある2万個以上の遺伝子のうちがんの発症・進展に関連する100~500の遺伝子を網羅的に解析する技術で、わが国では固形がんを対象として2019年より保険適用となった検査である。これにより、ゲノム医療の本格的運用が開始された。造血器腫瘍と固形がんにおける変異遺伝子が異なることから、産学共同で造血器腫瘍に対する遺伝子パネル検査の開発が進められているところであり、2023年度内の臨床実装が見込まれている。
造血器腫瘍におけるプレシジョン医療は患者の臨床所見・各種検査所見を総合的に判断した正確な「診断」と「予後予測」に基づき、患者にとって最も適切な「治療」を選択することであり、造血器腫瘍分野の発展に大きく影響を及ぼすことが期待される。
造血器腫瘍に特化した遺伝子パネル検査の開発
前述の通り、固形がんと造血器腫瘍では対象となる遺伝子が異なるため、わが国では2023年の保険適用を視野に造血器疾患に特化した遺伝子パネル検査の開発が進められている。この検査の特徴は、約400の遺伝子変異・再構成が検出可能であることから融合遺伝子の検出率が向上している点や、腫瘍由来DNAの解析に加え、口腔粘膜といった正常組織由来DNAを同時解析することで病的変異をより高い頻度で検出できる点、そして生殖細胞系列の病的変異の検出が可能である点などが挙げられる。このように、遺伝子パネル検査は非常に高い精度の結果が期待されるが、その一方で、遺伝性疾患への慎重な対応が求められる検査であることも留意すべき点である。
遺伝子パネル検査の運用に向けた課題
造血器腫瘍の遺伝子パネル検査を保険診療で実施する際には、いくつかの課題が残されている。その一つが、現行の保険診療下における固形がんの遺伝子パネル検査は、限られた施設のみで実施されるという点である。2022年10月現在においては、「がんゲノム医療中核拠点病院(12施設)」「がんゲノム医療拠点病院(33施設)」「がんゲノム医療連携病院(188施設)」であり、これらに該当しない施設では取り扱うことができない。また、実施施設に関連する課題としては、検査結果返却の過程で多職種(がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等)による検討会「エキスパートパネル」の開催が必要要件とされている点も挙げられる。エキスパートパネルは、遺伝子パネル検査の中でも非常に重要な役割を果たしているが、現状では「がんゲノム医療中核拠点病院」及び「がんゲノム医療拠点病院」のみでの開催となる。このような状況を踏まえ、造血器腫瘍と固形がんの遺伝子パネル検査を同じ枠組みで実施するかどうかといった現実的な運用体制の構築について、さらなる議論が必要とされた。