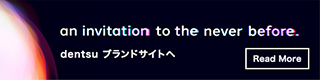近年、「Patient Centricity(患者中心の医療)」が盛んに提唱されています。今回は「Patient Centric」を企業の礎とし、患者志向の医薬マーケティングをサポートするトランサージュ株式会社の瀧口慎太郎様に 「人々の“生きる”を支える」を軸に、メディカル・ヘルスケア領域でメディカルプロデュースを行う株式会社電通メディカルコミュニケーションズの二木政和が、「Patient Centricity」の考え方についてお話を伺いました。
後編では、「Patient Centricity」の実現のためにどう考えるかについてお話をお話しいただきました。
「Patient Centricity」の実現に必要なことは、
患者さんの「行動」「考え」「感情」を知ること
瀧口:トランサージュでは、患者さんや家族のSNS投稿を拾い集め、Patient Reader®というソーシャルリサーチを行っています。リサーチを行っていて実感するのは、「患者さんは、本当に情報を欲しがっているのだな」ということです。特に、がん領域や希少疾患の患者さんは、ネット検索で思ったような情報が得られないことも多いようで、情報収集に苦労されています。また、自分と同じ境遇の患者さんの話を聞きたがっています。
二木:病気に関しては、患者さん本人だけではなく、家族や周りの人に知ってもらうことも大切だと思います。
瀧口:そうですね。領域によっては、医師や看護師、介護施設等、多くのステークホルダーが患者さんの疾患について情報共有しなければなりません。そうしたステークホルダーと共に、患者さんがどのようなことに困り、どのような生活を望んでいるのかについても知ることが大切です。私たちも、ソーシャルリサーチで患者さんの声を一つずつ拾っていく過程で病気のつらさを初めて知ることも多いですし、調査を依頼した製薬企業の方も、生半可な気持ちで治療薬や病気に向き合ってはいけないと改めてお気づきになることも多くあります。患者さんをサポートする側がこうした気持ちを持つことは非常に大切であり、患者さんのアウトカム向上のための原動力になるのではないかと思います。
二木:言葉や文章というのは読む人によって解釈が変わってしまうこともありますから、患者さんが実際に使ったリアルな言葉や表現、文脈そのものを共有しないとリアルに伝わらない部分もあるかと思います。
瀧口:おっしゃるとおり、言葉はすごく大切だと思います。予想以上に定量調査だけで済ませるケースも多いですが、定量的な結果だけでは患者さんの真のインサイトを理解することは難しいです。
二木:定量調査は、最大公約数的な傾向の把握には適していますが限界もあるのではないかと思います。トランサージュ様では、患者さんが病気や症状を認識してから最終的に医療機関への受診や治療に至るまでの行動や考え、感情などを示す、ペイシェント・ジャーニーを作成することも多いと思いますが、実際は一般的なものとは異なるジャーニーをたどる患者さんもいることから、多様な患者さんをすくい上げていく必要もあるのではないでしょうか。
瀧口:確かにペイシェント・ジャーニーは、最大公約数的にマッピングすることが多いかもしれません。なぜならば、ペイシェント・ジャーニーはターゲットセグメントのジャーニーが最も大事だからです。とはいえ、がん領域や希少疾患におけるターゲットセグメントのペイシェント・ジャーニーを描くことは難しいのではないかと思います。ペイシェント・ジャーニーだけですべての患者さんについて考えていくことはできませんが、ペイシェント・ジャーニーを作成する過程で多くの患者さんの行動や考え、感情を知る機会が得られる点は、患者さんの困りごとやニーズの確認に有益だと思います。
二木:少数派であっても、困っている患者さんはいらっしゃるので、患者さんの声を拾い上げる行為自体は「Patient Centricity」という観点からも重要だと思います。
瀧口:そうですね。これに関しては、デジタルマーケティングの考え方に似ているかもしれません。最初は全体的なターゲット層に向けて情報配信します。その後、顧客の行動特性を分析してターゲット層をブレイクダウンし、個別化された情報配信を行っていきます。今後、医療サービスもそのように導かれていくのかもしれません。
二木:今はその入り口に立ち始めたという時期なのかもしれません。今後、「Patient Centricity」の考え方を踏まえた上で、個別化された情報提供を行う際にはどのようなことが大切になってくると思われますか?
瀧口:やはり、最も大切なのは患者さんをきちんと知ることです。やはり、患者さんの本音を知ろうとする前向きな努力をし続けることはとても大切だと思います。私たちのソーシャルリサーチでは、患者さんのSNS投稿を介して生の声を収集し、分析していますが、これは製薬産業だけではなく医療という枠組みにおいても「Patient Centricity」に貢献できるサービスだと思っています。また、医療従事者の皆さんは必ずしも科学的なエビデンスだけを望んでいるわけではなく、「患者さんの生の声を知りたい」というニーズも確かに存在します。こうした現場のニーズに合わせた情報を収集・提供していくことで、医療従事者に寄り添った情報提供ができるようになるのではないかと思っています。
二木:医療従事者や患者さんに寄り添うためには、それぞれの望んでいることを知る必要があるということですね。
瀧口:実際のところ、患者さんの望みをすべて理解することは難しいですが、それでも少しずつでも歩み進み続けていかなければならないと思っています。製薬企業では、購買行動プロセスのAMTULモデル※などを用い、購買行動プロセスのステージに応じたメッセージの伝達を行っていると思います。しかし、レギュレーション上、提供できるメッセージに限りはあるかもしれませんが、どのようにそうしたニーズに寄り添うかが、差別化のポイントになると考えられます。
※ Awareness(認知)、Memory(記憶)、Trial(試用)、Usage(日常利用)、Loyalty(固定利用)のマーケティングの態度変容モデル
二木:製薬企業が行う情報提供活動にはさまざまな制約がありますから、どの企業も製品ブランドに込めた本当の思いをダイレクトに伝えられないというジレンマを抱えていると思います。私たちも、製薬企業の本当の思いを伝えるために何かできることはないかと日々、試行錯誤しています。

これからの医療コミュニケーションについて
二木:新型コロナウイルス感染症の流行で、多くの人のデジタルリテラシーが向上したように思います。最近では、高齢者もWeb会議システムを使いこなしていますよね。
瀧口:ソーシャルリサーチの際に、製薬企業の方から高齢者の患者情報を得ることができるかと問われることがありますが、60歳代から70歳代の患者さんでもSNS投稿を行っている人も多く、収集自体は可能です。世の中のデジタルスキルの向上を日々、実感しています。
二木:そうですね。今は幅広い年代でデジタルスキルの向上がみられます。
瀧口:こういった調査結果を同じ境遇で悩んでいる多くの患者さんに伝えるために、企業に紐付かない建て付けでのプラットフォームを組み立てられないかと考えています。今後、そうしたプラットフォームができれば、患者さんが本当に知りたいと思っている情報を得る機会を創出できるかもしれません。結果として、患者さんのアウトカムや治療満足度の向上への支援にもつながるのではないかと思っています。
二木:そうですね。患者さんを中心に考えていくと、今やるべき課題が次々と出てきます。
瀧口:製薬企業や医療従事者の方をサポートする立場として、我々も何らかの行動を起こせないかと模索しているところです。その一方で、配信されている情報を正しく患者さんが受け取るためのリテラシー向上への働きかけも必要だと思います。
二木:それと、患者さんのヘルスリテラシー向上も必要になってきますね。
瀧口:はい、それも重要だと思います。
二木:「Patient Centricity」の推進を考えていくと、医療現場、製薬企業、そして私たちマーケティング企業が今なすべき課題が自ずと見えてきました。私たちは、私たちが思っている以上に多くの課題を抱えていると感じました。本日は貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。