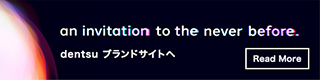メディカル領域を軸とする電通メディカルコミュニケーションズから、電通グループにおけるヘルスケア領域への取り組みを「ヒト」を通してご紹介します。
あらゆる場面において「コンプライアンスの重要性」が叫ばれる昨今、広告制作においても、法律に従って適正に進めることが必須事項となっています。なかでもメディカル・ヘルスケア領域は規制が厳しく、より厳密な取り組みが必要です。
今回は、メディカル・ヘルスケア領域の広告表現における法律との向き合い方について、株式会社電通コーポレートワン 法務・コンプライアンスオフィス 法務部 ディレクターの星弁護士に、株式会社電通メディカルコミュニケーションズの新田執行役員がお話を伺いました。
後編では「適切な広告表現」と、「法律と向き合う姿勢」について、より詳しくお話しいただきました。
広告表現の判断方法
新田:星さんは、これまでに多くの広告表現に関する相談を受けていらっしゃるかと思いますが、「こういう表現はアウト」、「これは一見アウトなようでいて、実はセーフ」といったように、検討の参考になる例が蓄積されるといったことはありますか?
星:広告表現は、広告内容全体から適法性を判断するので、「こういう表現はアウトで、こういう表現はセーフ」といったように形式的に判断できる場合は限られます。そのため、それぞれの法律の規定を個別の広告表現に適切に当てはめて判断することが大切です。事例の蓄積という意味では、例えば、景品表示法に関して言えば、実際に措置命令が出された事例をみて、消費者庁等が具体的な表示物について、どのような事実認定をしているのかを知っておくことは大事だと思います。措置命令事案を追うことで、消費者庁が現在執行に力を入れている不当表示の類型も知ることができます。また、薬機法に関しても、不適広告事例を公表している自治体もあるので、具体的にどのような表現が問題となるのかを把握することができます。東京都が主催する講習会でも薬機法の広告規制の概要とともに問題となる具体的なケースが例示されて分かりやすく解説されていますので、こういった講習会に参加することで実際の広告の適法性を判断する際の参考にできると思います。世の中の変化に応じて新しい表現も日々生まれていますし、関連情報を常にチェックするなどして、知識をアップデートできるように努めています。
新田:例えば「他社が同じような表現をしているのだから、ウチでもできますよね?」といった相談を持ちかけられることもあるのではないでしょうか。
星:そうですね。広告表現の審査をしていると、そのようなことを言われる場合も多いです。しかし、似たような表現に見えても、そもそも商品の内容が違っていたり、表示内容の裏付けとなる科学的根拠が異なっていたりする場合も多いので、個々の商品に応じて可能な表現なのかは精緻に検討しなければなりません。また、そもそも行政がすべての広告について事前にお墨付きを与えているなら「他社もやっているから問題ない」と言えるのかもしれませんが、当然そのようなことはありません。実際に措置命令などを受けているのは世に出ている広告なのですから、他社の広告も適法であることが担保されているわけではないのです。他社の広告は広告審査をする上で参考にはなりますが、批判的な視点をもって検討することが必要だと思います。
新田:たまたま指摘されていない、あるいは気づかれていないだけで、法律的には問題となる表現の場合もありますよね。
星:おっしゃる通りです。消費者庁も含めた行政機関がすべての広告を調査して法執行することは不可能ですから、法律上は問題のある広告でもいまだ指摘を受けていないだけということは多くあります。
広告表現を適切に判断するためには
新田:そういったなかでの判断基準は、どのようなものになるのでしょうか?
星:個々の法律によっても異なりますが、その広告などを目にする一般消費者がどのような印象や認識を抱くのかが重要な判断基準となります。法律の問題というと、法律の専門家の意見を仰げばよいと考えられがちですが、広告規制の分野では、一般消費者としての感覚を持ち合わせることが肝心です。私は広告規制をずっと専門的に扱っていますが、自分でも意識していないと目が曇ってしまうというか、どうしても法律の専門家としての立場から見てしまって、一般消費者の感覚から離れてしまっているのではないかと自問することがあります。
新田:「一般消費者の目線で」判断するために、広告表現の審査実務ではどのようなことをされていますか?
星:判断に迷う時には、法律の専門家ではないさまざまな人の意見を聞くようにしています。私自身もどちらかというと謙抑的に判断することが多いですが、たとえ法律に明確に違反するものでなくとも、「この広告は正義・道義に反するのではないか」という意見にはよく耳を傾け、そういった意見を尊重するように心がけています。あとは、これは法律の問題だけに限りませんが、社会の変化に応じて人々の価値観も常に変わっていますので、いわゆる炎上をしてしまった広告だけでなく、さまざまな広告が世の中にどのように受け止められているのかを検証し、日々学ぶようにしています。専門家であることに甘んじず謙虚な姿勢を持ち続けることが重要だと考えています。
新田:自身の意見が必ずしも一般消費者の意見とはニアリーイコールではない部分があるのをきちんと認識することが、より適切な広告表現をつくることにつながっていくということですね。
星:もちろん広告制作に携わる方は、日々そのようなことをされていると思います。「こういう広告を打てば人々の心に響くのではないか?」と考えるのは、その広告に触れる人を想定して、その人の立場になって考えるということですから。しかし、ただ注目を集めたり、商品が売れたりすればいいというのではなく、「この広告は誰かをだましたり、傷つけたりしないだろうか」といったような素朴な正義感をもって広告をチェックすることも大切だと思います。
特に健康に関連する広告の場合は、過剰な表現が時には人の生命や健康に関わるような場合もあるわけです。「この広告を世に出した時に、誰かが苦しむことにならないだろうか?」と常に考えることが重要です。
広告規制との向き合い方
新田:あとはいろいろな分野で「適正広告ガイドライン」も出されていますので、そういったものもきちんと踏まえたり、法務に相談したりしながら慎重に仕事を進めることも必要ですね。
星:広告会社は、「広告表現のプロでなければいけない」と思います。広告規制に抵触する表現を用いた広告をクライアントに納品するのは、プロとして失格です。広告制作に携わる者として、関連する基準やガイドラインをしっかりと認識し、法律の専門的な部分に関しては我々にも相談しながら、制作を進めていただきたいですね。
新田:車を運転するのも道路交通法などを理解して免許を取得し運転するわけですから、基本的な法規はまず頭に入っていなければいけないということですね。ただ、プロのドライバーであっても、実際に道路に出たら想定外の出来事が生じ、事故を起こすことがある。そうならないように、法務の方にさまざまなアドバイスをいただきながら進めていくということでしょうか。
星:はい。広告制作に携わる者として関連する法令等を認識しておくことは当然のことですが、自身が認識できていない法的な問題があるのではないかと慎重に考えることも必要です。少しでも不安に思ったら、法務に確認していただきたいと思います。
新田:我々が関わることが多い医療用医薬品の広告・資材制作は、ちょっとした間違いが患者さんの生命に関わる場合もあります。そのため、確認や審査は非常に厳しいのですが、慎重さや正確性は、決してゆるがせにはできないものと認識しています。
消費者に対して誠実な広告を
星:広告は、薬機法や景品表示法のみならず、著作権や商標権、肖像権、パブリシティ権など、さまざまな法律問題が集約する場です。そのため、複雑な法律関係を整理した上で、法律上問題のないものとする必要があります。しかし、必ずしもそれだけで十分ではありません。私は、広告審査は人格的な判断が求められる場でもあると思っています。法律的な面だけでなく、倫理的な面も踏まえて「この広告は消費者や世の中に対して誠実といえるか」を突き詰めて考えなければいけません。「誰に対しても誠実で、自分が心から誇れる仕事をしているか?」と常に自問自答しながら日々の業務を行っています。
新田:電通メディカルコミュニケーションズは「人々の“生きる”を支える」を社のビジョンとして掲げていますが、携わる仕事が誰かの喜びや幸せに結びつくかもしれないと考えることが、「誇れる仕事」を行うことにつながるのではないかと思います。
星:繰り返しになりますが、薬機法は医薬品などの品質や有効性、安全性の確保などによって保健衛生の向上を図ること、「国民の生命・健康を守る」ことが目的です。広告づくりもそれに反することなく、人々の喜びや幸せに結びつくように、誠実に行ってほしいと思います。
新田:大変参考になるお話が伺えました。本日はありがとうございました。
前編はこちらから。