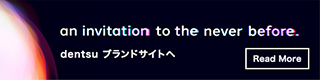メディカル領域を軸とする電通メディカルコミュニケーションズから、電通グループにおけるヘルスケア領域への取り組みを「ヒト」を通してご紹介します。
あらゆる場面において「コンプライアンスの重要性」が叫ばれる昨今、広告制作においても、法律に従って適正に進めることが必須事項となっています。なかでもメディカル・ヘルスケア領域は規制が厳しく、より厳密な取り組みが必要です。
今回は、メディカル・ヘルスケア領域の広告表現における法律との向き合い方について、株式会社電通コーポレートワン 法務・コンプライアンスオフィス 法務部 ディレクターの星弁護士に、株式会社電通メディカルコミュニケーションズの新田執行役員がお話を伺いました。
前編では、「ヘルスケア関連の広告に関わる法律」、「対象となる広告の定義とは?」などについてお話しいただきました。
医薬品や化粧品、食品広告の違いと、それぞれが関わる法律
新田:電通グループが制作に携わる広告については、さまざまな観点から「適正か否か」のチェックが行われています。まず、そういった「広告表現のチェック」に関する電通法務部での取り組みについてお聞かせいただけますでしょうか。
星:法務部では、一般的な企業で法務部が担当する、契約書の審査や法律相談などを主に行っていますが、私の場合は、景品表示法を所管する消費者庁の表示対策課に3年間勤務していた経験があることから、広告表現のチェックや販売促進のために景品を提供するキャンペーンに法的な問題がないかの確認を行う業務も担当しています。また、広告表現のチェックに関しては、法務部に加えて広告表現の専門チームである株式会社電通 クリエーティブ&ナレッジ推進センター 広告表現コンサルティング部が広告制作部門からの相談を受けています。
新田:医薬品や食品の広告に関しては、消費者の安全を守り不利益を回避するため、主に厚生労働省(厚労省)が医薬品と化粧品について、消費者庁が食品についての規制を担当していますが、厚労省の管轄では「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)、消費者庁の管轄では「景品表示法」や「健康増進法」などの法律が関わってきます。この辺りがかなり複雑ですので、簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか?
星:まず、どの商品や役務(サービス)の広告(表示)にも適用される、最も基本的な法律は「景品表示法」です。景品表示法は、実際の商品等の内容よりも著しく優良であると示す「優良誤認表示」などを、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるとして禁止しています。景品表示法は、医薬品や医薬部外品、化粧品などにも適用されますが、「薬機法」はこれらのものに関して虚偽・誇大な広告を禁止する規定を特に定めています。また、「健康増進法」は、表示規制の観点では、食品における健康保持増進効果等についての虚偽・誇大な表示等を禁止しています。
新田:基本的に景品表示法は「すべての商品やサービスに対するもの」で、薬機法は「医薬品などに対するもの」、健康増進法は「食品に対するもの」ということですね。
星:はい。ただし、気をつけていただきたいのは、食品であっても薬機法の対象になることがあるという点です。例えば、単なる健康食品であるにもかかわらず、「がんに効く」といったように医薬品的な効能効果を広告でうたってしまうと、当該食品は医薬品と判断されて「承認前の医薬品等の広告」を禁止する薬機法に抵触してしまいます。このように、薬機法は医薬品の虚偽・誇大な広告だけを規制しているのではなく、食品について医薬品的な効能効果を訴求すること自体を禁止しています。景品表示法が実際のものよりも優良であることを示す表示を禁止しているのに対し、薬機法は実際にその食品にそういった効果があるか否かは問われません。そういった意味で、薬機法の当該規定は、「医薬品的な効能効果」という特定の表現自体を規制しているという点が、景品表示法とは異なる特徴といえます。
新田:特定の表現というと、化粧品広告などの場合は、薬機法で「表示できる効能が56項目」と制限されていますが……。
星:化粧品広告は、表示できる効能が「肌にツヤを与える」、「肌を滑らかにする」など、具体的に示されています。その範囲を超える表現をすることはできません。
規制対象となる「広告の定義」とは?
新田:ところで、その対象となる「広告」ですが、「なにが広告なのか?」、「なにをもって広告とするのか?」ということもありますね。
星:景品表示法は、「広告その他の表示」を規制対象としているため、いわゆる「広告」であるか否かは問われません。景品表示法上の「表示」の定義に該当すれば、「広告」としてイメージされるテレビCMや新聞広告でなくとも規制対象となります。
他方、薬機法では、規制対象となる「広告」の該当性は、「広告の三要件」と呼ばれる三つの要件を満たすか否かによって判断するとされています(「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」〔平成10年9月29日医薬監第148号〕)。その要件とは、「1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること」、「2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること」、「3. 一般人が認知できる状態であること」の三つです。この三つの要件を満たす場合に、薬機法の規制対象となる「広告」と判断されます。
新田:それを逆手に取って、具体的な商品名は出さずに医薬品的な効果をうたっている例も見受けられます。
星:そうですね。広告三要件のうち「2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること」という要件を逆手に取って、商品に含有されている特定の成分の効能効果を表示しながら、具体的な商品名を記載しないことによって薬機法の広告規制を回避する手法が見られます。こういった「成分広告」と「商品広告」を形式的に分ける手法は、消費者庁内でも以前から問題視されていました。そこで、消費者庁は、あくまで景品表示法と健康増進法の「表示」の解釈に関して、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」という健康食品の表示に関するガイドラインを2022年に一部改定した際、「特定の食品や成分の名称を商品名やブランド名とすることなどにより、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に接した一般消費者に特定の商品を想起させるような事情が認められるとき」には、景品表示法や健康増進法の規制対象となる「表示」に当たるとの考え方を示しました。商品名を記載していない場合でも、一般消費者に特定の商品を想起させるのであれば、特定の商品に誘引するような事情が認められるとして、規制対象となることを明確にしました。薬機法の「広告」該当性の判断においても、今後はより実質的に判断される可能性もあると考えられます。
新田:一般消費者に特定の商品を想起させ、成分の効能効果と商品が結びついてしまえば、景品表示法や健康増進法の規制対象と判断される可能性があるということですね。 我々電通メディカルコミュニケーションズが業務の中心としている「医療用医薬品」に関しては、医療関係者以外の一般人を対象とした広告が制限されていたり、また依頼主の大半を占める製薬会社側の「医療用医薬品プロモーションコード」などの自主規制がとても厳しいため、常に正確さとともに、過剰なプロモーションの抑制も求められたりするといった現状があります。命に関わることもある薬剤ですから一般消費財とは大きく異なるのは当然なのですが、近年、電通グループからの要望でサポートさせていただく一般用医薬品や化粧品などに関しては、やはり「商品をいかに知ってもらうか」、「どのように使っていただきたいか」をより積極的に考えなければならないことも多く、表現に関しては常にせめぎあいがあると感じています。
健康に関わる広告表現に求められるもの
星:私が広告表現をチェックする場合に常に念頭に置いているのは、「その法律の趣旨や目的に立ち返る」ということです。例えば、薬機法は医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保や医薬品等の使用による保健衛生上の危害発生等防止のために必要な規制を行うことによって保健衛生の向上を図ることを目的としています。それはすなわち、「国民の生命・健康を守る」ということです。できるだけ訴求力のある広告表現をしたいという要望も理解できますが、それよりも「この広告を世に出した時に、誰かの生命や健康に危害が及ぶことはないのか?」を一番に考え、日々広告に向き合っています。
新田:法律本来の目的を忘れずに広告活動を行うことは、確かにとても重要ですね。
薬機法に関しては、最近の話題で言えば2021年に改正薬機法が施行されて、課徴金納付命令制度や措置命令制度が導入されたことも挙げられます。これについても少しご解説いただけますでしょうか。
星:はい。課徴金納付命令制度は、医薬品等の虚偽・誇大広告に関し、その販売で得た経済的利益を徴収することによって、違反行為の抑止を図り、規制の実効性を確保するための措置です。原則として、違反を行っていた期間における対象商品の売上額の4.5%の課徴金を納付しなければなりません。対象行為は、医薬品等の虚偽・誇大広告等の禁止を定めた薬機法66条1項に違反する行為です。承認前医薬品等の広告の禁止を定めた薬機法68条に違反する行為は、課徴金納付命令の対象外とされています。医薬品等の虚偽・誇大広告の規制対象者は「何人も」とされていますが、医薬品等の販売者以外の媒体社や広告会社は、一般的には課徴金納付命令に係る「取引」を行っていないため、課徴金納付命令の対象にはならないと考えられています。
措置命令制度では、「違反広告の中止」や、「違反したことを医薬関係者及び消費者に周知徹底すること」、「再発防止策を講じること」、「違反行為を繰り返さないこと」などが命じられます。対象行為は、課徴金納付命令制度とは異なり、医薬品等の虚偽・誇大広告だけでなく、承認前医薬品等の広告も対象となります。また、規制対象者は「何人も」とされており、媒体社や広告会社も措置命令を受ける可能性があります。
新田:そうすると、措置命令に関しては制作を担当する広告会社も、会社の信用棄損につながるレピュテーションリスクなどが発生する場合もあるということですね。
星:そうですね。現在のところ(2023年4月現在)、これらの制度の執行事例はありませんが、日々広告を審査するなかで、事業者の意識は確実に高まっていると感じます。課徴金納付命令制度の導入に伴う虚偽・誇大広告の抑止効果については、厚生労働科学研究班による抑止効果検証も行われています。
また近年は、承認前医薬品等の広告違反で、広告会社の役員らが逮捕されたり、アフィリエイターが書類送検されたりした事例もあります。薬機法は「何人も」が規制対象となりますので、広告会社においても「広告主の判断」に委ねることは適切ではなく、広告主とともに適正な広告宣伝活動を主体的に行う姿勢が大切であると思います。
後編では、「適切な広告表現と、法律への向き合い方」に関して、より詳しくお話を伺います。
後編はこちらから。