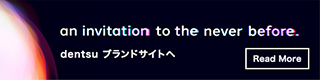2023年5月17~20日の4日間にわたり、第124回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 総会・学術講演会が福岡国際会議場(福岡県福岡市)において開催された。昨年は現地およびオンラインでのハイブリッド形式であったが、今年は現地開催と一部セッションのオンデマンド配信で実施され、会場は多くの参加者で賑わいをみせていた。
耳鼻咽喉科および頭頸部外科が扱う領域は幅広く、頭蓋底から上縦隔にまで及び、そこに聴覚・嗅覚・味覚・平衡感覚を担う感覚器や、咀嚼・嚥下機能、音声言語・呼吸機能などが含まれる。耳鼻咽喉科領域だけでなく、頭頸部外科の認知拡大のため、2021年に学会名を「日本耳鼻咽喉科学会」から「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会」へと名称変更している。
主要プログラムとして、宿題報告では「HPV 関連中咽頭癌 ―制圧への処方箋―」(大阪大学 猪原秀典教授)、「中耳真珠腫の病態解明と粘膜再生による新たな治療戦略」(東京慈恵会医科大学 小島博己教授)の2演題が、臨床講演では「嗅覚障害―病態に基づく診療アプローチ―」(金沢医科大学 三輪高喜教授)、「上気道炎症の病態と制御―臨床における疑問に挑む―」(滋賀医科大学 清水猛史教授)の2演題が行われた。さらに、シンポジウムでは医療DXやジャパンヒアリングビジョン(新生児から高齢者まで全世代の難聴対策の指針)などをテーマに取り上げ、パネルディスカッションでは新型コロナウイルス後遺症や難聴児への多職種連携支援などについて意見交換がなされた。
ここでは、学術集会最終日である5月20日の演題より一部抜粋して紹介する。
シンポジウム3
医療DX-診療システムのパラダイムシフト-
「進化し続ける情報技術が人々の生活を豊かにしていく」という概念であるDX(デジタルトランスフォーメーション)に関して、予防、診断、治療、障害福祉などといった医療分野においても新たなシステム構築が進められている。 本シンポジウムでは4名の演者が講演された。武見敬三氏(参議院議員)からは、新型コロナウイルスのパンデミックで露呈した日本の医療における課題として「危機管理体制」 「医療情報システム」 「ワクチンを含む創薬力」の3点が挙げられ、現在の日本における医療DXへの取り組みに関する推進状況について解説された。高尾洋之氏(東京慈恵会医科大学先端医療情報技術研究部准教授)からは、医療DXとタブレット端末などのアクセシビリティ機器を使ってQOLの向上を図るため、2018年に自身が発症した重症ギランバレー症候群の治療経験と日常生活におけるタブレット端末のアクセシビリティ機能活用事例も踏まえて解説された。黑川友哉氏(千葉大学助教)からは、「耳鼻咽喉科領域におけるモバイルヘルスのイマとミライ」というテーマで、デバイスのみならず技術を用いた医療のあり方からモバイルヘルスの定義について考察し、さらに医療機器と非医療機器の理解の重要性、モバイルヘルスを活用した医療開発への期待などについて解説された。水野佳世子氏(京都大学デジタルヘルス学助教)からは、リアルワールドデータを用いた臨床疫学研究について、医療系データベースを用いた臨床研究の詳細とその限界、それを克服するための統計手法の開発・進化などについて解説された。
教育講演8
発語運動障害(dysarthria)診療の手引き
Dysarthriaとは、原疾患による神経筋の障害に伴い生じる話しことばの異常であり、小児から高齢者まで見られる病態である。発語運動における呼吸・発声・構音・調音の強調運動といった遂行過程に関与するもので、失語症や発語失行とは異なる。コミュニケーション障害による社会生活への支障だけではなく、呼吸困難や嚥下障害などによる緊急対応を求められる障害である。
現在、dysarthriaは保険傷病名では「運動障害性構音障害」と翻訳されているが、その他にもさまざまな翻訳名称があり、合意が取れていない状況である。そこで、西澤典子氏(北海道大学客員臨床教授)は、dysarthriaの定義・病態、そして翻訳名称の変遷について解説され、“研究者が共有している病態を適切に表現し、かつ患者を含む社会全体にも理解されやすい翻訳名称を用いるべき”との観点から、「発語運動障害」という翻訳名称を提唱された。西澤氏は、今後も適切な翻訳名称に関する議論をさらに深める必要があると講演を締めくくった。 また、苅安誠氏(潤和会記念病院リハビリテーション部言語聴覚士)からは、「Dysarthria 診療の手引き」(日本音声言語学会 言語・発達委員会)の要点について解説された。本疾患の診断・評価のためには医師と言語聴覚士(ST)の連携が欠かせない。医師が診断において、発話音声や全身・局所の神経学的所見を検査することで診断し、STが発話異常や発生発語障害の原因・病型を特定し、評価と鑑別診断を行う。治療においては、原疾患の治療がdysarthriaを改善させる可能性が高く、対症療法やリハビリも有効である場合もある。これまで世界的にdysarthriaの診療指針となるガイドラインは存在しなかったが、日本音声言語学会 言語・発達委員会により2016~2022年にかけて検討が重ねられたこの「Dysarthria 診療の手引き」に大きな期待が寄せられている。