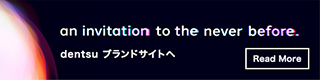2023年10月19、20、21日の3日間にわたり、第61回日本癌治療学会学術集会がパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて開催された。日本癌治療学会は、がんの予防、診断および治療に関する研究の連絡や提携・促進を図り、がん治療の進歩普及に貢献し、学術文化の発展や人類の福祉への寄与を目的とする学会である。
第61回学術集会のテーマは、「がん診療、一気通貫 ―力を合わせて、相乗効果―」とされた。これには、医療者視点からの医療技術の発展と、患者視点からの領域・職種横断的構図を背景とするがん診療において、それぞれの専門分野の垣根を越え一丸となって本学会の意義を再認識する機会にしたいという思いが込められている。
このテーマのもと、今回の学術集会では、がん治療に関連するシンポジウムやワークショップに加え、政界や文学界など医学分野以外の専門家による講演も開催されるユニークな内容の学術集会となった。
今回は、「一気通貫」をテーマとした会長講演を抜粋して紹介する。会長講演は藤原俊義氏(岡山大学・消化器外科学)司会のもと、本学術集会の会長である大家基嗣氏(慶應義塾大学・泌尿器科学教室)のライフワークである腎癌研究において、「原点回帰」「異分野融合」などを意識しつつ、常に新規性を探求し、常識を覆すことに挑んできた教室の歩みを紹介された。
会長講演
一気通貫と相乗効果による癌研究から治療へのループ
泌尿器の3大がんとは、前立腺癌、膀胱癌、腎癌だが、それぞれのがんの特徴は異なり、治療方針も異なる。例えば、大家氏がレジデントとなった1990年頃は、早期の腎癌に対する部分切除(腫瘍の部分だけを切り取ること)は禁忌とされていた。それは、腎癌は複数のがんが発生する「多中心発生」と考えられていたからである。同じく、前立腺癌と膀胱癌も多中心発生であることが明らかにされていたが、腎癌も果たしてそうなのかと疑問を持った大家氏は、全摘除術後108個の腎癌標本から連続切片を作成し、腎癌における多中心発生は極めて稀であることを証明した。この研究成果の発表以降は、早期の腎癌に対し部分切除は一般的となり、標準治療を変えるに至った。
その後も、シグナル伝達、血管新生などの分子レベルの研究が活発に行われ、そこからさらに新たな概念により生み出された免疫チェックポイント阻害薬が登場すると、バイオマーカーの検索が盛んに行われるようになった。このように、研究テーマは微小病変~分子レベル~微小病変の探索へとループして原点へと回帰し、まさに今回の学術集会のテーマを象徴していることが述べられた。
このほか、がんの研究に発生学的視点を取り入れ、がん細胞の転移は発生における細胞の移動に通じており「先祖返り」しているのではないかとの仮説から、ドセタキセル抵抗性をリバビリンによって感受性に戻した世界初のリプログラミング治療は、異分野融合による「相乗効果」であるとの見解が示された。
最後に、腎癌研究は微小病変の探索から端を発し、現在の研究テーマである癌免疫微小環境の一細胞解析につながっていること、相乗効果のがん研究とは発生学と腫瘍学を融合させて創薬を目指していることについて述べられ、講演は締めくくられた。