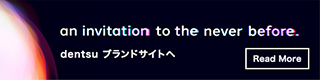去る2024年6月6日~8日、「Endocrinological Journey Never Stops」をテーマに、第97回日本内分泌学会学術総会が神奈川県横浜市のパシフィコ横浜ノースにおいて開催された。
内分泌に関わる多領域の叡智が横浜に集結
周知のとおり、内分泌領域には視床下部・下垂体疾患、甲状腺疾患、副甲状腺疾患、副腎疾患、膵内分泌疾患、性腺疾患といった多臓器が関係する数多くの疾患が含まれる。このため、本総会においても内科医のみならず、産婦人科医・小児科医・泌尿器科医・脳神経外科医など幅広い診療科から多数の医師が参加した。
本学会は、2026年に創設100周年という節目を迎えるということもあり、「日本内分泌学会支部会の歴史と100周年に向けた取り組みについて」と題された特別企画では、北海道から九州までの9つの支部長から、支部会ごとの現状の活動報告や100周年に向けての意気込み、今後の方針などが語られた。そして本セッション最後のクロージング・リマークスでは、“内分泌学津々浦々(Endocrinology Across the Nation)”を合い言葉に、学会員が一丸となって100周年、さらにはその次の100年を見据えて、内分泌代謝学の学術・研究の発展、人材育成、社会貢献・啓発活動、グローバル化、ダイバーシティのさらなる推進を目指していくことが確認された。
本総会のハイライトは、「“優れた臨床内分泌科医”を目指すために第97回日本内分泌学会学術総会にご参加いただいた皆様と一緒に考えたいこと」をテーマにした会長講演である。慶應義塾大学医学部の“Best Teacher Award”を幾度となく受賞している長谷川奉延会長が、特に若手・中堅の医師に向けて、「“優れた臨床内分泌科医”とは、患者・家族、医療関係者、社会(第三者)から高い満足度が得られる医療を提供できる医師のことである。“優れた臨床内分泌科医”を目指すには、診療技術などのテクニカルスキルはもちろんのこと、患者・家族に行動変容を起こしてもらうべく、communication・patient educationを中心としたノンテクニカルスキルにも磨きをかけるべきだ」と強調した。
また、特別企画講演「人間の認知を解き明かす -体感する無意識領域」では、マジシャンとしても活躍する、精神科医・日本認知科学研究所の志村祥瑚氏が、「“錯覚や思い込み”などの認知バイアスは、特に“言葉・視点・比較”によって無意識に誘導されやすい」ことをテーブルマジックのデモンストレーションを行いながら披露した。
日本は、世界に類をみない超少子高齢社会を迎えている。教育講演5「内分泌疾患としての不妊症-保険診療時代の治療を踏まえて-」で語られたように、生殖医療による出生数は今や7万人に迫り、全出生児の8.6%を占めるに至っている。そうした中で、生殖医療の保険適用条件が2022年4月から拡大されたこともあり、生殖医療に対する社会の注目度は否応なく高まってきている。また、シンポジウム9「高齢者・超高齢者の内分泌代謝疾患の特徴を理解する」で討論されたように、認知機能障害、うつ状態、ADL低下、サルコペニア、フレイル、転倒・骨折などの老年症候群をきたしやすい高齢患者への対応は喫緊の課題となっている。
内分泌領域では、2022年度から日本専門医機構が認定する内科系サブスペシャルティ専門医として「内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医」が新たに制定され、新制度での認定試験が開始されたことが記憶に新しい。少子高齢化が急速に進むわが国において、日本内分泌学会の会員医師らが、それぞれの専門性をもってこれら多くの社会課題に取り組んでいくことが期待される。